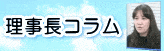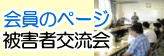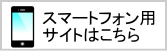���e�ؖ��X�ւ̉��
���e�ؖ��X�ւƂ́A���{�X�֊�����Ёi�X�ǁj��舵���X�֕��ł��B��ʂ̗X�֕��Ɠ��ɈႤ�Ƃ���́A �X�֕��̕����̓��e���ؖ�������ʂȗX�֕��ł��B
�ؖ����镶���͓��{�X�֊�����Ђ����{�ɂ���ďؖ����鐧�x�ƂȂ��Ă��܂��B
�����Ɉ�������z�B�܂ł̑��B�ߒ����L�^����鏑���Ƃ��Ĉ����܂��B
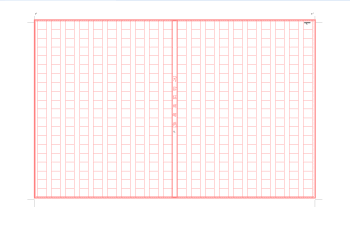
�@�I�S���͓͂��ʑ��B�قǂ̌��ʂ͂Ȃ����A���e�ؖ��́A�u���i���o�������t�j�A�N���i���o�l�j�A�N�Ɂi����j�A
�ǂ̂悤�ȕ����̓��e�̎莆���o�����̂��v�Ƃ������Ƃ����̈ϑ��������{�X�ւ��ؖ����邱�ƂŁA�������ɏؖ��������ƂƂȂ�܂��B
�Ȃ��A�u�z�B�ؖ��v��t���邱�Ƃɂ���Ĕz�B���ꂽ���t���ؖ�����܂��B
��ʓI�ɓ��e�ؖ���p����悤�ȏꍇ�́A
�@�I�����̂��߂̏؋��Ƃ��邱�Ƃ�z�肵�Ă��邱�Ƃ������̂ŁA�z�B�ؖ��ƕ��p���邱�Ƃ��ƂĂ��d�v�ł��B
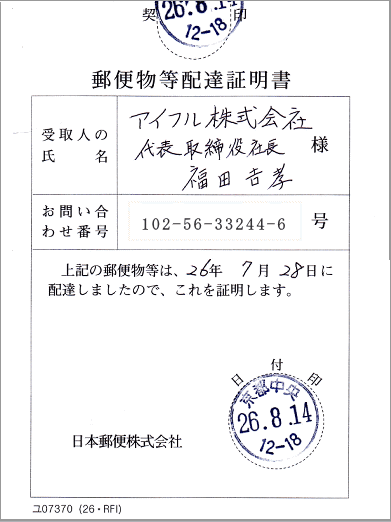
���ɁA�����o�������t�����w�m����t�x�Ƃ����Ă��܂��B �@����A�m����t�����邱�Ƃ��v���ƂȂ��Ă�����̂�����܂��̂ŁA ��Ϗd�v�Ȗ����������Ă��܂��B
�������A�ؖ��������͕̂����̓��e�Ƒ��݂ł���A �����̓��e���^���ł��邩�ǂ������ؖ�������̂ł͂���܂���B
�����̉��p�ʒm�ɁA���e�ؖ��͕K�{�����ł͂���܂��A����̂��߂ɓ��e�ؖ��Œʒm���邱�Ƃ��]�܂����̂ł��B
�K��̔��E�d�b���U�E�}���`���@�Ȃǂ̃N�[�����O�I�t���x�ł́A ����̋Ǝ҂���N�[�����O�I�t�Ɋւ��鏑�ʂ��Ƃ��Ă�������ԓ��ɒʒm�����Ȃ���Ȃ�܂���B �t�Ɍ������̊��ԓ��ɔ����_�����������ӎv�\���������ؖ����K�v�ƂȂ��ł��B
����Ȏ��̌���̏؋��Ƃ��āA���̓��e�ؖ��X�ւ𗘗p����̂��ł����ʓI�ȕ��@�ł���Ǝv���܂��B���e�ؖ����g���āA ������Ƃ����_������̏��ʂ��o���A���Ȃ����u���N���������Ɂv�A�u�ǂ�ȓ��e�̕������v�A�u�N�ɑ��āv������������X�ǂŏؖ����Ă����̂ł��B�@
�Ȃ��A�X�����c���ɂƂ��Ȃ��A����܂ŗX�E���������҂́A���ׂČ��������疯�ԉ�̎Ј��ƂȂ������߁A
���{�X�֊�����Ђ̎Ј��̒����瑍����b���C�������u�X�֔F�؎i�v�����e�ؖ��̔F���邱�ƂȂ�܂����B
���e�ؖ��X�ւɂ́u���̗X�֕��͉��N���������扽���������e�ؖ��X�֕��Ƃ��č����o���ꂽ���Ƃ��ؖ����܂��B�v
�̕���������A�X�֔F�؎i�̓��t������Ă���̂ŁA���i�ȃC���[�W������A������������ʒm�l�ɂ́A
����Ȃ�́u�S���I�������ʁv������Ƃ����Ă��܂��B
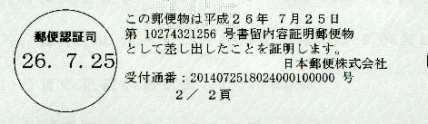
���߂ē��e�ؖ������l�Ȃ�A�����ƈႤ��ۂ̗X�֕����͂��A�u���̏��ʓ��B��P�O���ȓ��Ɏx���Ȃ��ꍇ�͖@�I�[�u�E�E�v
�ȂǂƋL�ڂ���Ă���ƁA���͈�̉��������̂��낤�ƍl���Ă��܂��̂ł��B
�܂��A��L�̃C���[�W�ɂ���悤�ȐԂ��r���̓������p���ő����Ă���Ɠ��Ɉٗl�Ȋ��������܂��̂ŁA�����ʓI�ȏꍇ������܂��B
���e�ؖ��X�ւ͈�ʓI�ɂ�A�S�A�a�S�ł������A�g�p����p���́A��{�I�ɂ͎莆�ł��̂ŁA
�ǂ�ȗp�����g�p���Ă����܂��܂���B��Ⳃ⌴�e�p���ł������p���ł����܂��܂��A�m�[�g��j���ď����Ă��悢�B �傫�������R�ł��B
�c�����������ǂ���ł�OK�ŁA�菑���ł����[�v�������ł����܂��܂���B
�������A���e�ؖ��X�ւł́A�ʏ�̎莆�ƈ���ē����̎莆���R�ʁi����ȏ�̏ꍇ������j�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�菑���ł���Ώd�˂ăJ�[�{�����𗘗p���ĕ��ʏo������x�̔�r�I�����p���̕��������Ă��܂��B�s�̂̃��m�ɂ͕֗��ȃm���J�[�{�����ʗp���ɂȂ��Ă��郂�m������܂��B
�܂��A�ꖇ�̗p���ɏ����镶���̐������܂��Ă���̂ŁA���e�p���̂悤�Ƀ}�X�ڂ̂�����������Ղ��̂ŕ֗��ł��B
�Q�l�ł����A�u���{�@�߁v�Ƃ����Ƃ���̓��e�ؖ����̗p�������[��X���Ŕ̔�����Ă��܂��B
�Ȃ��A�X�֖@�ɂ���ĉ��L�̂Ƃ���K��������܂��B
������ŁA �t���[�̌r���t�̓��e�ؖ��X�֗p�����_�E�����[�h�ł��܂��B �菑��������ꍇ�ɂ́A�ƂĂ��֗��ł��B
��������
�P���̗p���ɋL�ڂł��镶�����̐���
�c�����̏ꍇ�E�E�E�E�P�s�Q�O���ȓ��A�P���Q�U�s�ȓ�
�@�������̏ꍇ�E�E�E�E�P�s�Q�U���ȓ��A�P���Q�O�s�ȓ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �P�s�Q�O���ȓ��A�P���Q�U�s�ȓ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �P�s�P�R���ȓ��A�P���S�O�s�ȓ�
��Ǔ_�@�A�B�͊e�P���Ƃ��܂��B
�u�v�A()�Ȃǂ̊��ʂ́A�܂������Ă���ꍇ���P���Ƃ��Ĉ����B
�@�@�@���Ƃ��A�u�����ς݁v�Ȃ�T���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�j���j�Ȃ�R���B
�����␔�����~�A�O�p�`�A�l�p�`�Ȃǂ̘g�ň͂��̂́A�e�����Ƙg�i1���j�̍��v�ƂȂ�B
�@�@�B�͂Q���A�I�͂R���A![]() �͂R��
�͂R��
���ʕt���̐����ŁA�����\���L���Ɣ��f�����ꍇ�͑S�̂łP���ł��B
�@�@(1)�_��� (2)���z (3)�����@�Ȃ�P�O��
�@�@�@ �_��� �A ���z �B �����@�ł��P�O��
�L����P��
�@�@�@�� �͂P���A�u �͂Q���A�s �͂Q��
�X�y�[�X�͕����A�s�Ƃ��ɃJ�E���g���܂���B
�p�����Q���ȏ�ɂ킽��ꍇ�ɂ́A�z�`�L�X�ŕЂƂ����āA�܂�ڂɗ��y�[�W�ɂ܂������ē�܂��B
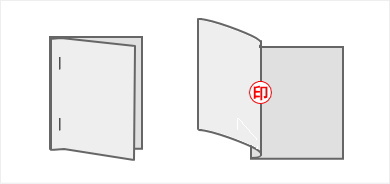
��������
���e�ؖ��X�ւŎg�p�ł��镶���́A�Ђ炪�ȁA�J�^�J�i�A�����A�����ł��B
������123�E�E�̎Z�p�����ł��A���O����Q�̊������ł��g�����Ƃ��o���܂��B
�O����͎g�p�ł��܂���B
�������p���́A�����A��Ж��A�n���A
���i�������ŗL�����ɂ͎g�p�\�ł��B
���̑���ʓI�ȋL���͎g�p�ł��܂��B
����
���t���搔�{�Q���ƂȂ�܂��B
�X�ǍT���P���A���o�l�T���P���ƂȂ�܂��B
���肪�P�l�Ȃ瓯�����̂R���K�v�ł��B
�R�s�[�̏ꍇ��1���͏����āA����2���̓R�s�[�ł����̂ł��B
�������A�v�����g�A�E�g�A�J�[�{�������ʁA�Ȃ�ł�OK�ł��B
�����E�C��
����������A�폜�����������͔��ǂł���悤�ɓ�d���������A�Y���ӏ��̗��O�Ɂu�R�������v�u�P�������v�̂悤�ɏ����Ĉ�������܂��B ��͍��o�l�̈�Ɠ������̂��g���K�v������܂��B
- �@�����̍폜
- �������폜���邾���̏ꍇ�́A�폜���镶���̏��
��d���������܂��B
���O�ɂ́u���s�ځ����폜�v�Ə����A ��������܂��B
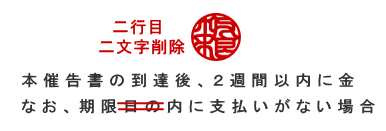
������Ղ��悤�ɐԎ��ŋL�ڂ��Ă��܂����A���ۂɂ͍����ŋL�ڂ��邱�ƁB
- �A�����̉���
- ��������������ꍇ�́A�c�������@�������ɂ��g���ĕ�������������B���O�ɂ́u���s�ځ��������v�Ə����A ��������܂��B
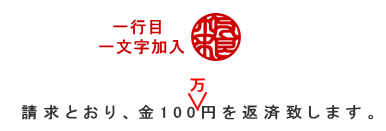
- �B�����̒���
- �����������Ԉ���āA�����������ꍇ�́A�����ԈႦ���������d���������č폜���������ŁA�������̏ꍇ�͒�����ɁA
�c�����Ȃ璼�����ɒ��������������L�ڂ��܂��B���O�ɂ́u���s�ځ��������v�Ə����A��������܂��B
���������ꍇ�ɂ��A �P�s�ɏ����镶�����͕ς��܂���̂Œ��ӂ��ĉ������B
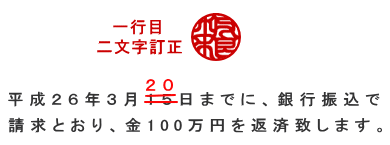
���
�ʏ�A���o�l�����̉��i�������Ȃ�E�j�ɁA��܂����A������Q���ȏ�ɂȂ�Ȃ���Έ�ӂ͓��ɕK�v����܂���B
�������A���{�ł́A�d�v�ȕ����ɂ͓������܂��B��͂�A���{�̕����Ƃ��ďd�v�ȏ��ʂɂ͊ԈႢ�Ȃ��{�l�̈ӎv�ō쐬���ꂽ���̂Ƃ��ē�������M�p�x��d�v�x����������ɓ`���ƍl���܂��B�o����Έ�ӂ͎g�p���܂��傤�B
�����̂���ꍇ�⊄��K�v�ȏꍇ�͕K����K�v�B
���������ۂ̈�Ɠ������m�������܂��B �F���OK�B
��O�Ƃ��āA�O���l�̏ꍇ�ɁA������⊄���̂����ɃT�C���ł��悢���ƂɂȂ��Ă��܂��B
����
�{���ŏ������Z�������Ɠ����łȂ���Ȃ�܂���B
���́A���Ȃ��ŁA�X�ǂɎ����Ă����܂�
�������k �� �m�o�n����҃T�|�[�g�Z���^�[���
���{�X�ւ��z�B���s�����Ə��̂���X�ǂ���ѓ��{�X�ւ��w�肷��ꕔ�̗X�ǂ̑����݂̂̎戵�ƂȂ��Ă��܂��B
�傫�ȗX�ǂȂ�A�����Ă������Ă��܂����A�������o�����Ǝv���Ă���ߏ��̗X�ǂ���舵���Ă��邩�͎��O�ɓd�b�ł����āA �m�F���Ă���s���܂��傤�B
�Q�O�O�P�N�Q������A�C���^�[�l�b�g���g���āA�����o�����e�ؖ��X�փT�[�r�X���n�܂�܂����B
����́A�C���^�[�l�b�g��ʂ��ėX�ǂɓ��e�ؖ��X�ւ������o�����@�ł��B���o�l���X�ǂɍs���K�v�͂���܂���B
�C���^�[�l�b�g��ʂ��č����o�����߁A�Q�S���ԂR�U�T����t�\�ł��B
�z�B�͒ʏ�̓��e�ؖ��X�ւƓ������X�Lj������ڎ��l�ɔz�B���܂��B ���肪�C���^�[�l�b�g����ɐڑ����Ă�����ɂ���K�v�͂���܂���B
�{���̍쐬�̓��[�h�Ȃǂ̃��[�v���\�t�g���g�p���܂��B�ʏ�̓��e�ؖ��X�ւƈႢ�P�s20���~�P��26�s�ȓ��̎�������������܂���B
�ڂ����́A�������HP�ŁI��e-���e�ؖ�
�������k�͂����� �� �m�o�n����҃T�|�[�g�Z���^�[
���e�ؖ��X�ւ̎���⎞�����p�葱���Ȃlj��ł����C�y�ɂ����k�������B����͉c����ړI�Ƃ��Ȃ�NPO�@�l�ł��B

�p : �������ꎞ�I�ɒ��f���邽�߂ɓ��e�ؖ��ōÍ����s�������ƍl���Ă��܂��B �����A�s���B�ɂȂ�Ǝ����͒��f���Ȃ��̂ł����H
�` : ���݂̗X�֎���͂ƂĂ��悭�Ȃ��Ă��܂��̂ŁA��z�E���z�Ȃǂ͋N����ɂ����Ȃ��Ă��܂��B
�������Ȃ���A100���Ƃ�����ɂ͂������A�H�ɂł͂��邪��z�E���z�͔������Ă���悤�ł��B
�܂��A���ʗX�ւł͑���ɓ��B�������ǂ������킩��܂���̂ŁA�����X�ւő������Ƃ��Ă��A���̕����̒��̎莆�ɂǂ�ȕ��ʂ��L�ڂ���Ă���̂��܂ł͕�����܂���B
�����A�؋��ԍς̍Í����s�����Ƃ��Ƃ����҂Ɏ咣�����Ƃ��Ă��A���҂�����ȏ��ʂ͓����Ă��Ȃ������Ɣ��_�����ƁA�@���I�ɂ͏ؖ��ł��܂���B
�����ŁA���e�ؖ��X�ւ𗘗p����ƁA�X�ǂ��莆�̓��e���ؖ����Ă����Ƃ������x�Ȃ̂ł��B �܂��A���̗X�ւ�������ɔz�B���ꂽ���Ƃ܂ł��ؖ����Ă���܂��B�i�z�B�ؖ��t���e�ؖ��ɂ����ꍇ�j�d�v�ȕ����͔z�B�ؖ��t���e�ؖ��ŏo���ׂ��ł��B
�ł́A�ݖ�̂悤�ɓ��e�ؖ��X�ւ�����s�݂Ȃǂŕs���B�ɂȂ�Ǝ������f�̍Í��ʒm�̌��ʂ͂Ȃ��̂ł��傤���H
�������f�̒ʒm������Ƃ��́A���@�ł͌����Ƃ��đ���ɓ��B���邱�Ƃ��v������Ă��܂��B �� �ٔ��O�̍Í�
�ӎv�\���͑���ɓ��B�����Ƃ��Ɍ��͂������܂��B�i���@�X�V���j����̃|�X�g�ɓ������ꂽ��A�����̉Ƒ���������ꍇ�ɂ�����ɓ��B�������ƂɂȂ�܂��B
�������A�ō��ٔ�����ꏬ�@�약��10�N6��11���̔����ɂ�茈�������Ă��܂��B ���l�Ɏ�̂̈ӎv������A���e�ؖ��X�ւ���̂��邱�Ƃ��ł��A�Љ�ʔO����l�̗��m�\�ȏ�Ԃɒu����A�x���Ƃ����u���Ԃ������������_�Ŏ��l�ɓ��B�������̂ƔF�߂���Ƃ���܂����B
����^�_���^ ���s�A����A�^�ޗǂ̕��^ ���������k���^ ���Ȕj�Y���
TEL�@06-6782-5811
�g�уT�C�g https://www.syouhisya.org/smarth/